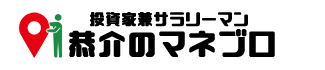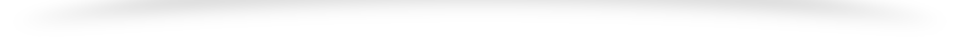痛み分けに
公的年金制度が2021年に改正されることをご存知でしょうか?
一言で言ってしまうと現役世代と受給世代で痛みを分け合う形になったのが大きな特徴です。
前回の2004年の改正では賃金が物価の伸びよりも低い場合の特例が設けられました。
賃金上昇率がマイナスにな多場合、物価に連動させる特例があります。
これによって年金以外に収入のない受給者に深刻な生活面への影響が出ないように配慮されました。
しかし今回の改正では、賃金上昇率がマイナスになったときに物価の変動に関係なく賃金の変化をベースに年金額が決められることになりました。
これで年金について中立的になりました。
ですから現役世代と年金をもらっている世代で痛みを分かつ内容になったと言われるわけです。
将来世代の付けを減らす制度も
年金改正ですが、実は2018年度にも実施されています。
これは少子高齢化に対する取り組みで、将来世代の負担を軽減することが目的です。
2004年度の改正でマクロ経済スライドが導入されました。
これは給付額の水準を調整することで財政の健全化を目指すのが目的です。
しかし当初特例が設けられていました。
原則通りに調整すると改定率がマイナスになる場合には、前年度の年金額を下回らないように調整されます。
またもし基本的な改定率がマイナスになった場合、調整が全く適用されない特例もあります。
しかしこれだと当面の受給者が損をしません。
一方で少子高齢化が続く今後への対応ができません。
そこで特例を適用したときの調整分を繰り越す形になりました。
調整前の改定率が高い時にまとめて生産することで、健全化のスピードを速めようというわけです。
実質的には目減りしている可能性も
このようにいろいろな特例や調整が行われているので、年金制度が複雑になっています。
名目上は受給額がアップしているけれども、実質的には逆に目減りしていることもあり得ます。
例えば2019年度と2020年度には先ほどの少子高齢化に適応するための調整が実施されました。
ですから表面上の年金額は前年度比アップしているはずです。
しかし実質的な価値で比較していると、むしろダウンしているわけです。
不平等さをなくすことが今後の課題
年金制度の改正は今後も行われるでしょう。
これまでは年金受給世代の方に手厚く給付される仕組みが続いていました。
しかし少子高齢化の進む今後、このアプローチでは破綻する懸念も出てきています。
そこで高齢者にも負担をしてもらうというシステムに今後さらに変更していく可能性は大です。
野党の中には「年金カットだ」と批判する向きもあります。
しかし高齢者の占める割合が4割以上に今後なる可能性が高い現状では、高齢者に負担を強いるのも致し方ないでしょう。